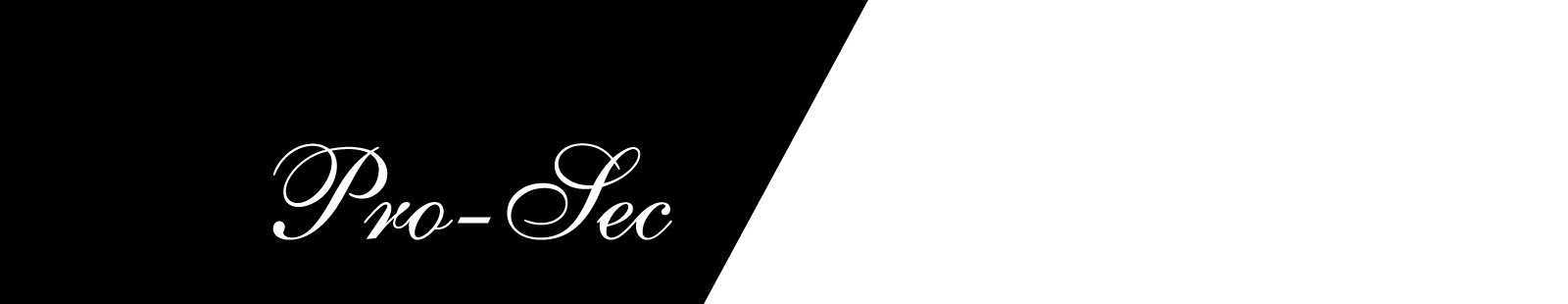年度始めの4月が近づいています。
早いものでちょうど2年前の4月より、私は大学院で秘書にかんする研究を行い、この春、修士号を取得して修了の運びとなりました。
この2年間の学びを経て、切に感じている我が国の秘書を取り巻く近々の課題としては、いわゆる来客応対やビジネス文書などの業務を担当する「間接補佐型秘書」から、経営サポートにもコミットすることができる「直接補佐型秘書」を育成するための教育の確立が急務であるということです。
我が国においては、この間接業務といわれる業務は、一般的には女性秘書が担当するケースが多いのが現状ですが、間接業務の多くは、もはや外注化されたり、AIにとって変わられる可能性が高いため、これらの業務をコアな業務とする秘書は、淘汰されていくことは必定です。
また、このような間接補佐を業務とする女性秘書が、女性活躍推進の流れの中で管理職に昇格しているケースが散見されます。
しかし、管理職として活躍するのであれば、間接補佐業務ではなく、直接補佐業務といわれる経営サポートや人材育成、また、組織マネジメントなどを遂行する能力が不可欠です。
このように昨今の社会の急激な変化を受けて、秘書や秘書機能のあり方も大きく様変わりし続けていますが、いわゆる秘書室や秘書部といった、ある程度の規模の秘書機能をもつ企業では、「総理大臣秘書官」のような組織形態をとるケースが増えています。
つまり、内閣であれば、各省庁から生え抜きといわれる人材が集結して、総理を補佐するように、企業であれば、各部門の実務に精通したスペシャリストが、チームとしてトップを補佐するというスタイルです。
かつて昭和の時代は、経営企画室などを経験した男性が秘書として登用されるケースが多くみられましたが、いまや数字や経済に精通している秘書だけでは、トップの補佐が務まる時代ではありません。
それぞれの専門分野や業務に精通した人材が、チームとしてトップを補佐し支える。
秘書や秘書機能も時代と共に進化が必須である以上、秘書の育成についても、新しい流れを構築することが急務です。